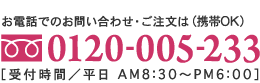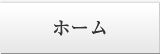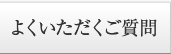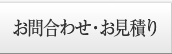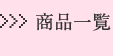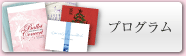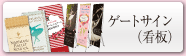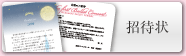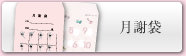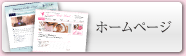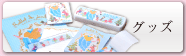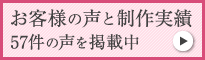


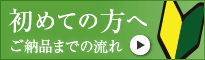




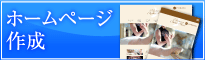
全国の都道府県対応です。
東京,神奈川,横浜,埼玉,大宮,
千葉,茨城,群馬,栃木
❖東北地方
青森,岩手,秋田,宮城,仙台,
山形,福島
❖東海/北陸/甲信越地方
愛知,名古屋,静岡,三重, 岐阜
石川,富山,福井,新潟,長野,山梨
❖近畿地方/中国/四国地方
大阪,京都,奈良,滋賀,兵庫
和歌山,岡山,広島,鳥取,山口
島根,愛媛,徳島,高知,香川
❖北海道
札幌市,旭川市,函館市
❖九州/沖縄地方
福岡,佐賀,長崎,大分,熊本,宮崎
鹿児島,沖縄,那覇市

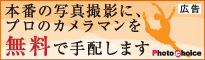


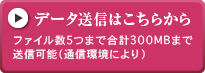
バレエプログラムブログ
「カルメン」を見ました。
原作のメリメの小説は、当時のスペインの民族的なことなど、社会的な背景をえぐったものだったと言われていますが、オペラやバレエなどでは闘牛をモチーフに取り入れるなど同国の陽性なイメージが全面に押し出されているようです。
日本でも一時期フラメンコブームによってスペインが注目されていましたが、スペインとカルメン=色っぽい女性というイメージを重ねる人は今でも少なくないのではないかと思います。
一人の男が、自由奔放な女カルメンに人生を狂わされて転落していくというストーリー、救いは何もない終わり方の割にはその暗さをあまり気にせずに楽しめるのは、良いのか悪いのか。
カルメンのアリア「ハバネラ」など耳に親しい音楽にも注目です。
「イヴァン雷帝」はもともとボリショイバレエの作品ですが、私が見た「イヴァン雷帝」は2004年パリ・オペラ座。
そのせいなのかどうか、あまりロシア臭がしないように感じるのは私だけでしょうか。
スラブの香りがしないのです。
雷帝のニコラ・ル・リッシュの異様な迫力もアナスタシアのエレオノーラ・アバニャートの美しさも素晴らしいことはもちろんなのですが、
ロシア的な感じがしないな、というのが最初の印象でした。
演出とか衣装とかそういったものに何か問題があるというわけではたぶんないと思うし、作品全体の価値が変わるわけでももちろんなく、私の中の
イメージと一致しないというだけのことだとは思うのですが。
そんな中で、私が「ロシアっぽい」と勝手に感じたのは、ラストシーンの鍵ともなっている道化者です。
イヴァンと親衛隊が鞭を振るって粛清をしていく中で、一人の道化が踊る。
その道化の中にいるのは実はイヴァン。その道化に首に縄をかけられてつり上げられて終幕。
ロシアという国、あるいは狂気に踊らされ、捕らえられて一生を終えたイヴァンを象徴しているのでしょうか。
イヴァンが生涯で最も愛したと言われる妻アナスタシア。一幕でも二幕でも密着度の高い二人のパドドゥが見られます。
特に二幕のパドドゥは、折りたたまれ、重なり合い、なまめかしい二人の時間が表現されています。
アナスタシア役のエレオノーラ・アバニャートが実に妖艶です。
イヴァンを恨む人々の陰謀によって毒を盛られ、瀕死の状態であるアナスタシアの足下にざわざわと伸びる人々の手が、地獄からの誘いのようにも感じられ、印象的でした。
終盤のアナスタシアの幻影とイヴァンとののパドドゥも、アナスタシアが本当に生身の人間ではない不可思議な存在のようにぴったりと張り付く動きを見せています。
グリゴローヴィチの振付けでは、イヴァンの内面の孤独さやアナスタシアとの夫婦愛がより引き立っていると言われます。
狂気じみた粛清の陰に本当は孤独な心があったのか、どうなのか。
残虐な帝王の内面が実は孤独で、愛を求めたというロジックは分かりやすいものではありますが、果たしてどうだったのでしょう。
酒池肉林に耽っていたという史実(とされるもの)からはあまりそういった内面は、私には伺えないのですが、そんなイヴァンの内面を想像しながらも楽しめる作品のように思います。
バレエの好みということで言えば、「マノン」や「椿姫」など、心理劇の要素が強いものが、何となく好きです。
それと対極にある、と私には映るのが、今日見ている「イワン雷帝」。
「ファラオの娘」に似た印象がありますが、主要キャラクターは少なく、群舞は多く、衣装も装置も壮大、といったところです。
モチーフとなっているのは、ロシア皇帝イヴァン四世。イヴァン四世の英名は「ivan the Terrible]」で、歴史に名を残す暴君と言われています。
残虐な方法で粛清を続けたイヴァンは反面、敬虔で宗教的な儀式を好んだということ。
孤独から神を求めていたのか、罪の意識から神を求めていたのか、この二面性はよく分かりません。
衣装の胸に刻まれている光る十字架に、雷帝の内面を考えさせられます。
アンソニーダウエルのことを書いていて、「田園の出来事」を思い出しました。
これはツルゲーネフの「村のひと月」が原作。
振付けはアシュトンです。
単品でDVDになっているものは知らないのですが、確か「グレートパドドゥ」や「ベスト・オブ・ナタリア・マカロワ」などのDVDで見られると思います。
本当は五幕もある戯曲を一幕にしたもの。
これもまたロシア作品にありがち(と私は思うのですが)で、図を描かないとわかりにくいような複雑な人間関係が、田園の別荘を舞台に描かれます。
こういう心理劇みたいなものは、ダウエルの得意とするところなのではないかと、勝手に思っています。
先日より書いている「三人姉妹」の続き。
このキャストの中でもっとも印象的なのは次女の夫、クルイギンを演じたアンソニー・ダウエルでした。
この人は本当に内面表現に秀でた人で、「マルグリットとアルマン」のアルマンの父親役が印象的です。
英国ロイヤルバレエ団の芸術監督も務め、最近では3年ほど前に来日公演もあったのではないかと記憶しています。
男性ダンサーと言うと、パワフルで高さがある人も多いですが、一人でくっきりと浮き立つのではなく、舞台全体に調和してしまうような、それでいて圧倒的な存在感がある、そういう人に感じられます。
クルイギンは、神経質、まじめ、融通がきかない田舎教師。しかし実直で深く妻を愛している。そんなキャラクターと抱えている苦悩が浮かび上がるパフォーマンスです。
それで先に書いた「三人姉妹」の中身についてです。
モスクワを離れ、没落してゆく三姉妹を中心に、その恋や生き様を描いた作品です。
独身の長女、早くに結婚し、誠実な夫に退屈して不倫の恋に走る次女、二人から求婚されながらも自分探しをしている三女の三人姉妹。
長女が次女の夫に心を寄せるあたり、ロシアっぽい。。。と思ってしまいますが、ここはマクミランの創作です。
演劇的なシーンも多く、前半から中盤にかけては、ディナーパーティーのシーンが無音で折々に挿入されています。
全編を覆っている陰鬱な雰囲気は、マクミランの振付とダンサーたちの演技力が作っているものなのでしょう。
モスクワへさえ帰れば幸せになれる、と言わんばかりの三人姉妹の希望に、青い鳥を追い求めてしまう人間の性を見る思いがします。
マクミランの「三人姉妹」を見ています。
英国ロイヤルバレエ団。
これはチェーホフの戯曲を元にしたロシアの三人姉妹の物語。
シェイクスピア素材のバレエ作品でも同じことを思うのですが、原作が翻訳されていても美しい台詞の数々である場合、文学として非常に魅力があるがゆえに、バレエ作品としてはどうなるのだろう、と思います。
この「三人姉妹」も原作の名台詞とも言うべき言葉を思い浮かべながら舞踊を追っていると、ちょっと物足りなく感じてしまうのが正直なところです。
また冒頭~前半の、込み入った関係が表現されていくくだりは、少し展開が早すぎるような感があり、もう少し叙情に浸りながら物語を味わいたいという気がしてしまいます。
もっともマクミランは、原作を再現するのではなく、イメージを表現しようとしたと言われていますから、台詞を思い浮かべながら、あるいは原作のテンポを思いながら見るという見方そのものが誤りかもしれません。
原作からさまざまなバリエーションが生まれている他の作品と同じように、全く別のものとして見るのが適当なのだとは思いつつも、染み付いた原作からなかなか離れられずにいます。
先日、新国立劇場の情報センターから「日本のバレエ~三人のパヴロワ」という本が出版されました。
資料集ということになっているし、今のところアマゾンでも見当たらないので、薄いガイド的なものかと思いきや、紹介ページによると112ページ。
アンナ・パヴロワ、エリアナ・パヴロワ、オリガ・サファイアについて書かれているもようです。
いわゆる、日本のバレエ界三人の恩人です。
アンナ・パヴロワは大正時代に全国各地で公演を行っています。エリアナ~は鎌倉にゆかりがあり、戦時中に日本軍の慰問に訪れた南京で亡くなったということ。ネット上で靖国に御霊がまつられているという記述も見つけて驚きました。
オリガ・サファイアも含めて、実に日本のバレエというのはロシアに負うところが大きいとあらためて思います。
気になる本なのですが、資料集という扱い・・・。買おうかどうしようか、少々悩んでいます。
ネットを検索していたら、素人の人が自由に問題を作れるページに、バレエ検定があったので、やってみました。
問題は8問であっという間。
質問の内容は初歩的で、バレエ用語や有名な作品の登場人物に関するものなど。
簡単、簡単と思っていたら。。。一問間違っていました(汗)。
ところで、「本物」のバレエ検定といえば、NAMUEのクラシックバレエ検定がありますが、誰でも受験できる(技能を伴わない)、知識的な検定ものも、バレエの周知のためにはあるといいのかもしれない、などとふと思いました。