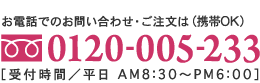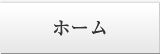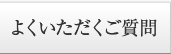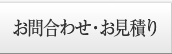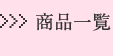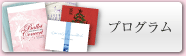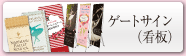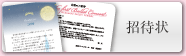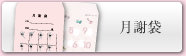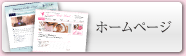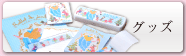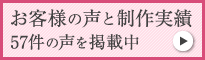


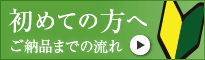




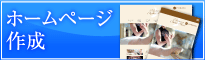
全国の都道府県対応です。
東京,神奈川,横浜,埼玉,大宮,
千葉,茨城,群馬,栃木
❖東北地方
青森,岩手,秋田,宮城,仙台,
山形,福島
❖東海/北陸/甲信越地方
愛知,名古屋,静岡,三重, 岐阜
石川,富山,福井,新潟,長野,山梨
❖近畿地方/中国/四国地方
大阪,京都,奈良,滋賀,兵庫
和歌山,岡山,広島,鳥取,山口
島根,愛媛,徳島,高知,香川
❖北海道
札幌市,旭川市,函館市
❖九州/沖縄地方
福岡,佐賀,長崎,大分,熊本,宮崎
鹿児島,沖縄,那覇市

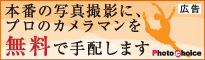


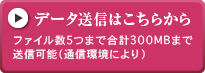
バレエプログラムブログ
先日、新聞の教育欄に、松山バレエ団が全国の小中高校で行っている巡回公演のことが取り上げられていました。
文化庁の子どもの文化芸術体験事業の一環です。
同事業はミュージカルや合唱など、さまざまな一流の団体が学校などで公演を行うというもの。
記事では、松山バレエ団が昨年神奈川県の小学校で行った「くるみ割り人形」の公演について、主に触れていました。
普段の5分の1ほどの広さの舞台で行われたという公演。観客と物理的にも、精神的にも近いゆえに、ごまかしがきかない舞台なのだろうと、想像しました。
ネットでその他の公演先を見ると、地方の学校も多く、バレエスクールが近郊にないのでは、と思うような地域もありました。
美しい、楽しいと感じる心が、しばしば芸術のスタートになります。
観客の子どもたちに、クリスマスの一夜の夢の物語がどのように響いたのか、想像するだけで楽しくなります。
パリ・オペラ座バレエ団のダンサーが、石巻と仙台でレッスン指導をしたニュースを読みました。
新聞記事などによれば、エトワールのドロテ・ジルベールら回転やジャンプなど基本動作を1時間半にわたって指導したといいます。
youtubeにもAFPニュースと思しきものがUPされていました。
新聞の記事はごく短かったのですが、こちらはインタビュー、レッスン風景とも、さまざまな映像がありました。詳細はわかりませんが、レッスンを受けた生徒の中には、東京での公演を見ることができる人もいるということです。
バレエスクールがどのような環境に置かれているのか、短い記事からは推し量ることができませんが、子供たちの笑顔のまぶしさが印象的でした。
真剣な様子と踊る喜びがひしひしと伝わってきて、とても美しいと感じるレッスン風景でした。
今朝の読売新聞の文化欄に、熊川哲也の話題が出ていました。
今月からオーチャードホールの芸術監督になった熊川さん。
2月2日からはいよいよ「シンデレラ」の上演です。
記事は、「シンデレラ」では演出や振付に専念して「出演はしない」というリードになっていて、リードに象徴されるように、ちょっと漠然とした内容ではありますが、芸術監督になった熊川さんの抱負が中心となっています。
記事中、「シンデレラ」について熊川さんは「キラキラ」という表現をしていました。主人公が心が美しいがために行けるキラキラ輝く世界。それが「オープニングに合うと思った」とのこと。「キラキラ」という言葉に、「シンデレラ」のイメージがふくらむ思いがしました。
自身の主演作では、自分に合わせた自由な振付だったけれども、今作は初日の王子役の宮尾俊太郎に合わせた振付といいます。これも後進育成、世代交代への序章なのでしょうが、どんな振付になってくるのか、本当に楽しみです。
ロミオとジュリエットはたった5日間の物語であるわけですが、何度か見ていても時々そのことを忘れてしまいます。
この5日間はジュリエットが女性として大きく変化する5日間であり、人生には遠浅の海のように、大きく人間が変わる時があるーというだれかの言葉を思い出します。
14歳であるという設定は常に頭の中にありますが、それでも違和感のないフェリのすごさ。
最初の部分では乳母のひざに軽やかに飛び乗ったり、お人形で遊んでいたり、それがまた自然な少女ぶりですが、舞踏会での恋のときめき、バルコニーでの官能的な情熱のパドドゥと、大きく変遷していきます。
しなやかに曲がるフェリの体はさながら美しい鳥で、本当に見応えのあるロミオとジュリエットでした。
ロミオとジュリエットのDVDについて、続きです。
アレッサンドラ・フェリのジュリエットは最高でした。
フェリのつくりもののような顔はもちろん美しいのですが、フェリの美しさの骨頂は手足ではないかと思います。
「ジゼル」の足も、人間ではなく、まさに妖精を思わせるものでした。
この作品ではジュリエットが、クラシックなチュチュではなく、ふんわりとしたワンピース?をまとっています。チュチュをまとう舞台の方がバレエらしい感じがして、個人的には好きなのですが、この方が足の動きがよりなまめいて見えるとあらためて思いました。
マクミランのパドドゥには、上方にひじを折ったポーズが何度か出てきます。
キリスト教のオランス=祈る人と呼ばれる救済祈願、あるいは至福の状態にある魂を示すそうで、ロミオに出会って幸せいっぱいのジュリエットの心境を表現しているといわれます。
このオランスのポーズでも、折った両手がとても美しく印象的でした。
ある意味、生身の人間ではないかのような手足がとても美しいと感じられました。
年明けの休日に、「ロミオとジュリエット」のDVDを見ました。
1984年、英国・ロイヤルバレエ団です。
あらためて、せりふなく、この難解な物語を表現しているバレエという芸術に感嘆します。そしてせりふがないがゆえに、たとえば演劇や小説ほどの救いのなさがなく、あくまで美しく感じられるーという気がします。
情熱的な男女の機微も、血で血を洗う両家の争いも、思わず息をのむような迫力がありながら、リアルとはやはり違うーその絶妙さがバレエなのかもしれません。
一方で古典のバレエにはない演劇性が、この作品の特徴のひとつです。
女性たちの靴も、トゥシューズではありません。
古典のバレエはシーンにかかわらず、舞台をかろやかに駆け抜けていくようなイメージを私は持っているのですが、この作品の登場人物は舞台上で住んでいるかのようなある種の重々しさを感じます。